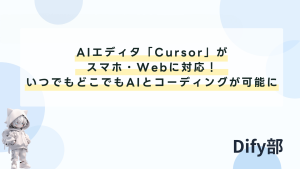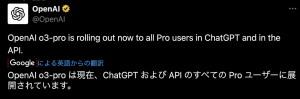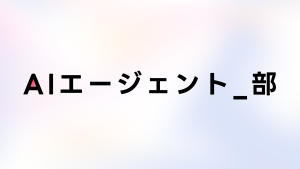MetaのCEO、Mark Zuckerberg氏は、超知能AI(スーパーインテリジェンス)の開発に向けた壮大な計画を発表しました。
今後、「数千億ドル(数十兆円)」という天文学的な規模の投資を行い、複数の「マルチギガワット(GW)級」のデータセンターを建設するというのです。Hyperion Data Centerに関してはマンハッタンと同じ程度の大きさのようです。
この発表は、AIの王座を巡る競争が、優秀な研究者の頭脳を奪い合う「人材獲得競争」から、国家規模の電力を飲み込む「計算インフラ戦争」という新たな、そしてより過酷な段階へ突入したことを告げるものです。
「敗北」から始まったインフラ戦争
この巨大な賭けの背景には、Metaが最近味わった「敗北」の記憶があります。
AIモデルの性能競争、特にオープンソース分野で中国のスタートアップDeepSeekに後れを取った事実は、社内で強烈な警鐘として受け止められました。
どんなに優秀な研究者を集めても、最高の計算インフラがなければ、最高のAIモデルは作れない。
この単純明快な事実が、Zuckerberg氏を「創業者モード」へと駆り立て、人材とインフラの両輪で競合を圧倒する、壮大な巻き返し戦略へと突き動かしたのです。
Zuckerberg氏は自身のSNS「Threads」で、「我々はビジネスから得た資本でこれを実行できる」と断言。これは、Metaの収益の柱である広告事業が生み出す潤沢なキャッシュを、AIという名の「軍拡競争」に惜しみなく注ぎ込むという力強い宣言に他なりません。
https://www.threads.com/@zuck/post/DMF6tMAxkX8
ギガワット時代の幕開け 「Prometheus」と「Hyperion」
Metaが計画するAIデータセンターの規模は、これまでの常識を遥かに超えています。計画の核心は、以下の二つの巨大プロジェクトです。
Prometheus(プロメテウス)
2026年にオハイオ州で稼働開始予定。1GWを超える計算能力を持つ、Meta初のギガワット級スーパーコンピュータークラスター。
Hyperion(ハイペリオン)
ルイジアナ州で建設中。
数年かけて最大5GWまで拡張可能な、まさに「巨人」級のデータセンター。「その敷地面積はマンハッタンのかなりの部分を覆う」とZuckerberg氏は表現しています。
ギガワット(GW)という単位
「ギガワット(GW)」という単位が、この競争の異次元のスケールを物語っています。
1GWは100万キロワットであり、これは大規模な原子力発電所1基分に匹敵する電力です。
つまり、Metaは原発数基分の電力をAI開発のためだけに消費するインフラを、複数建設しようとしているのです。
この動きはMeta単独のものではありません。AI覇権を争うライバルたちも、同様のインフラ戦争に突入しています。
| 企業 | プロジェクト名 | 規模(想定) | 拠点(一部) |
|---|---|---|---|
| Meta | Prometheus / Hyperion | 1GW〜5GW | オハイオ州、ルイジアナ州 |
| OpenAI/Microsoft | Stargate | 最大5GW | (非公開) |
| xAI (Elon Musk) | Colossus | ギガワット級 | テネシー州 |
| (非公開) | ギガワット級 | オハイオ州など |
興味深いのは、各社が自社のプロジェクトに「Prometheus(人類に火を与えた神)」「Hyperion(光の巨人)」「Stargate(星への扉)」「Colossus(巨像)」といった神話的、あるいはSF的な名前を付けている点です。
これは、彼らが目指す「超知能」が、人類の歴史を塗り替えるほどの力を持つという信念の表れなのかもしれません。
AIが飲み込む電力と環境への代償
「知性は、電力を変換して生み出される最も価値ある産物だ」。これは専門家の言葉ですが、AI開発の現実を的確に捉えています。
しかし、その「変換」には、社会が支払うにはあまりに大きなコストが伴う可能性があります。
ギガワット級データセンターが一つ稼働すれば、それは数百万世帯分の電力を消費します。すでに、The New York Timesは、Metaのデータセンター計画が原因で、ジョージア州の周辺住民の家の水道が枯渇する事態を引き起こしていると報じています。
専門家の試算はさらに衝撃的です。現在、米国の総電力消費量に占めるデータセンターの割合は2.5%(2022年時点)ですが、このままAI開発が進めば、2030年までにその割合は20%に達する可能性があるというのです。
これは、米国のエネルギーインフラ全体を揺るがしかねない、国家レベルの危機と言えます。
AI企業が掲げる「再生可能エネルギー100%での運用」という目標も、ギガワット級の巨大な需要の前では、あまりに非現実的に響きます。
技術革新の猛烈なスピードに、社会インフラの整備と環境への配慮が全く追いついていないのが実情です。
問われる「持続可能性」と「社会的合意」
Zuckerberg氏が点火したギガワット競争は、AI開発のボトルネックが、もはや半導体の性能やアルゴリズムの巧妙さだけではないことを浮き彫りにしました。
これからの勝敗を分けるのは、「安定した電力供給を確保できるか」、そして「地域社会からの理解、すなわち社会的合意を得られるか」という、極めて現実的な制約になるでしょう。
この競争は、私たちに根本的な問いを突きつけます。数千億ドルという巨額の投資と、破格の報酬で集められた天才たちが生み出す「超知能」は、私たちが支払うことになるエネルギー危機、水不足、環境破壊といった巨大なコストに見合う価値があるのでしょうか。
Metaの発表は、AI覇権争いが最終章に突入したことを示しています。
しかしその結末は、一握りの巨大テック企業が描く未来像だけで決まるべきではありません。AIがもたらす光と、それが落とす濃い影の両方を見据え、そのコストを誰が、どのように負担するのか。テクノロジー業界だけでなく、社会全体で議論すべき時が来ています。
まとめ
Metaの超知能AIへの巨額投資は、AI開発を国家インフラを奪い合う「エネルギー戦争」へと変えました。
原発数基分の電力を消費するAI開発は、その価値と環境破壊というコストのバランスが問われます。
今や勝敗を分けるのは、技術力だけでなく電力確保と社会的合意であり、社会全体での議論が不可欠です。